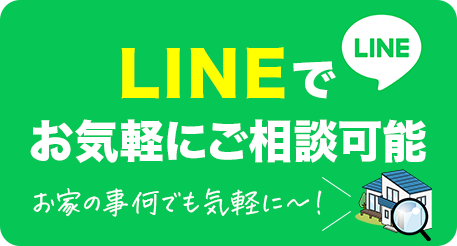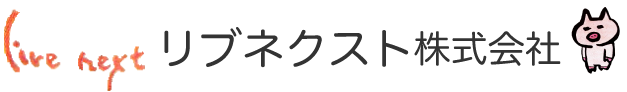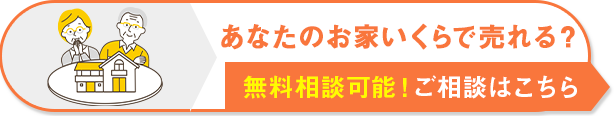家を売るための不動産売却の流れを5つのステップで解説|必要書類と方法紹介

監修者
山内康司
TikTokにて、不動産売却・購入について配信中。
不動歴10年以上。元警察官。

Contents
家を売るための不動産売却の流れを【5つのステップ】で完全解説|必要書類や成功のコツも紹介
家やマンションを「売る」と決めたものの、いざとなると「まず何から始めて、どういう順番で進むんだろう?」「どんな書類が必要になるの?」と、不安や疑問が次々に出てくる方も多いのではないでしょうか。
不動産の売却は、人生でそう何度も経験することではありません。だからこそ、しっかりとその「流れ」を理解しておくことが、後悔しないためにはとても大切です。
この記事では、不動産売却が初めてという売主さん向けに、売却が決まってからお金を受け取るまでの全プロセスを、大きく5つのステップに分けて、わかりやすく解説していきます。各ステップで必要になる書類や、スムーズに進めるための「コツ」も具体的にお伝えしますので、ぜひ最後までお付き合いください。
Step 1:売却準備 〜 まずは何から始める?
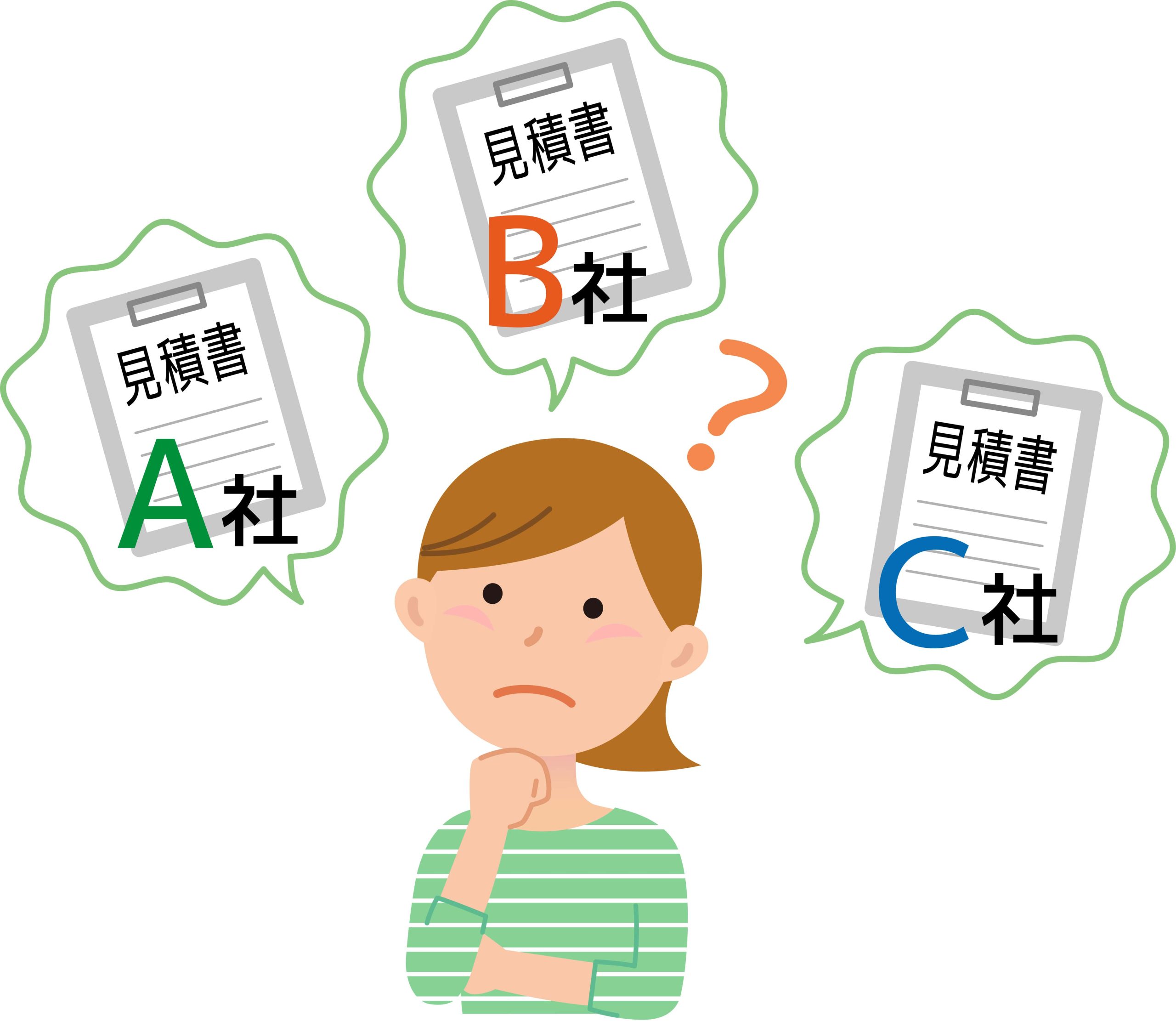
家を売ろう!と思い立ったら、まず最初にやるべきことがあります。それは「情報収集」と「自分の家の現状把握」です。
1-1. 相場を知る:「うちの家、いくらで売れる?」
多くの方が一番気になるのが、やはり「いくらで売れるか」ですよね。手始めに、インターネットの不動産ポータルサイト(SUUMOやHOME’Sなど)で、ご自身の家と似た条件(エリア、広さ、築年数など)の物件がいくらで売りに出されているか、いくつか見てみましょう。これが「相場観」を養う第一歩です。
より具体的に知りたければ、不動産会社に「査定」を依頼します。最初はネットで申し込める「机上査定(簡易査定)」で大まかな金額を知り、その後、実際に家を見てもらう「訪問査定」で、より正確な査定額を出してもらうのが一般的な流れです。
ここで非常に重要なのが、必ず複数の不動産会社(できれば3社以上)に査定を依頼すること。「査定額が会社によって結構ちがう」ことに驚くかもしれませんが、それこそが相見積もりの意味です。「なぜその金額なのか」という根拠を聞き比べることで、ご自身の家の適正な価格が見えてきます。
1-2. 家の「公式情報」を確認する
売却活動を始める前に、ご自身の家の「公式な情報」を正確に把握しておく必要があります。
- 権利関係の確認:法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、「所有者は誰になっているか(共有名義ではないか?)」「借金などの担保(抵当権)は設定されていないか」をチェックします。
- ローン残高の確認:もし住宅ローンがまだ残っている場合は、借りている金融機関に連絡し、「あといくら残っているか(ローン残高証明書の発行)」を確認します。売却価格でローンを完済できるかは非常に重要なポイントです。
- 家の詳細情報の整理:購入時のパンフレットや契約書、図面(間取り図、測量図など)、固定資産税の納税通知書など、家に関する書類を手元にまとめておくと、後の手続きがスムーズです。
1-3. パートナーとなる不動産会社を選ぶ
査定結果や集めた情報を元に、売却活動を任せる不動産会社(パートナー)を選びます。査定額の高さだけで決めるのは禁物です。
- 担当者の知識・経験:不動産売却に関する知識は豊富か? 地域情報に詳しいか?
- 販売戦略:どのように広告を出し、買い手を探してくれるのか? 具体的な提案はあるか?
- コミュニケーション:こちらの話をしっかり聞き、疑問に丁寧に答えてくれるか? 報告・連絡・相談は密にしてくれそうか?
- 契約条件:仲介手数料はいくらか? 契約期間は?
こうした点を総合的に見て、「この担当者になら安心して任せられる」と思える会社を選びましょう。
私たちリブネクストも、お客様一人ひとりのご事情に寄り添った売却活動を得意としています。「どこに頼めばいいかわからない…」という方も、ぜひ一度ご相談ください。
「リブネクストが不動産売却で選ばれている理由」も、パートナー選びの参考にしていただければ幸いです。
Step 2:媒介契約 〜 不動産会社との正式な約束
売却を任せる不動産会社が決まったら、その会社と正式に「売却活動をお願いしますね」という契約を結びます。これを「媒介契約(ばいかいけいやく)」と言います。媒介契約には、主に3つの種類があり、それぞれ「お任せ度」や「ルール」が異なります。
| 契約種類 | 特徴 | どんな人向け? |
|---|---|---|
| 一般媒介契約 | ・複数社と契約OK。 ・自分で買い手を見つけてもOK。 ・不動産会社の報告義務は任意。 ・契約期間は法令上の定めなし(通常3ヶ月)。 |
・広く買い手を探したい。 ・人気物件で、すぐ売れそう。 ・自分で探すアテもある。 |
| 専任媒介契約 | ・契約は1社のみ。 ・自分で買い手を見つけてもOK。 ・不動産会社は2週間に1回以上の報告義務あり。 ・契約期間は最長3ヶ月。 |
・1社にしっかり売却活動してほしい。 ・自分で買い手を見つける可能性もある。 ・(迷ったらコレを選ぶ人が多い) |
| 専属専任媒介契約 | ・契約は1社のみ。 ・自分で買い手を見つけるのもNG。 ・不動産会社は1週間に1回以上の報告義務あり。 ・契約期間は最長3ヶ月。 |
・売却活動を完全にプロに任せたい。 ・とにかく早く売りたい。 ・(不動産会社が最も力を入れる契約) |
どの契約が良いかは、売主様の状況や考え方によって異なります。担当者とよく相談し、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で選びましょう。契約書にサインする前には、仲介手数料の金額と支払い時期、契約期間、契約更新や解除の条件などをしっかり確認することが大切です。
Step 3:売却活動と条件交渉 〜 いよいよ買い手探しへ
媒介契約を結んだら、いよいよ本格的な売却活動がスタートします。不動産会社が主体となって進めますが、売主様にも協力していただく場面が出てきます。
3-1. 販売活動(広告・内覧)
不動産会社は、物件情報を不動産ポータルサイト(SUUMOなど)や自社ホームページに掲載したり、チラシを作成・配布したりして、広く買い手を探します。物件の写真撮影のために、室内をきれいに片付けておく必要があります。
購入希望者が見つかると、**「内覧(内見)」**の申し込みが入ります。売主様がまだ住んでいる場合は、日程を調整し、内覧当日は家をきれいに掃除・換気して、買い手を迎えます。内覧は売却成功の最大のチャンス。清潔感と明るさを心がけ、誠実な対応をすることが大切です。(内覧のコツは別記事で詳しく解説予定です)
3-2. 購入申し込みと条件交渉
内覧の結果、購入を希望する人が現れると、**「購入申込書(買付証明書)」**が提出されます。ここには、希望購入価格、手付金の額、契約希望日、引き渡し希望日、住宅ローン利用の有無などが記載されています。
売主様はこの内容を確認し、もし希望価格より低い金額が提示された場合などは、不動産会社を通じて**価格や条件の交渉**を行います。引き渡し時期についても、ご自身の引越しスケジュールと照らし合わせて調整が必要です。双方の条件が合意に至れば、いよいよ売買契約へと進みます。
Step 4:売買契約 〜 最も重要な約束事
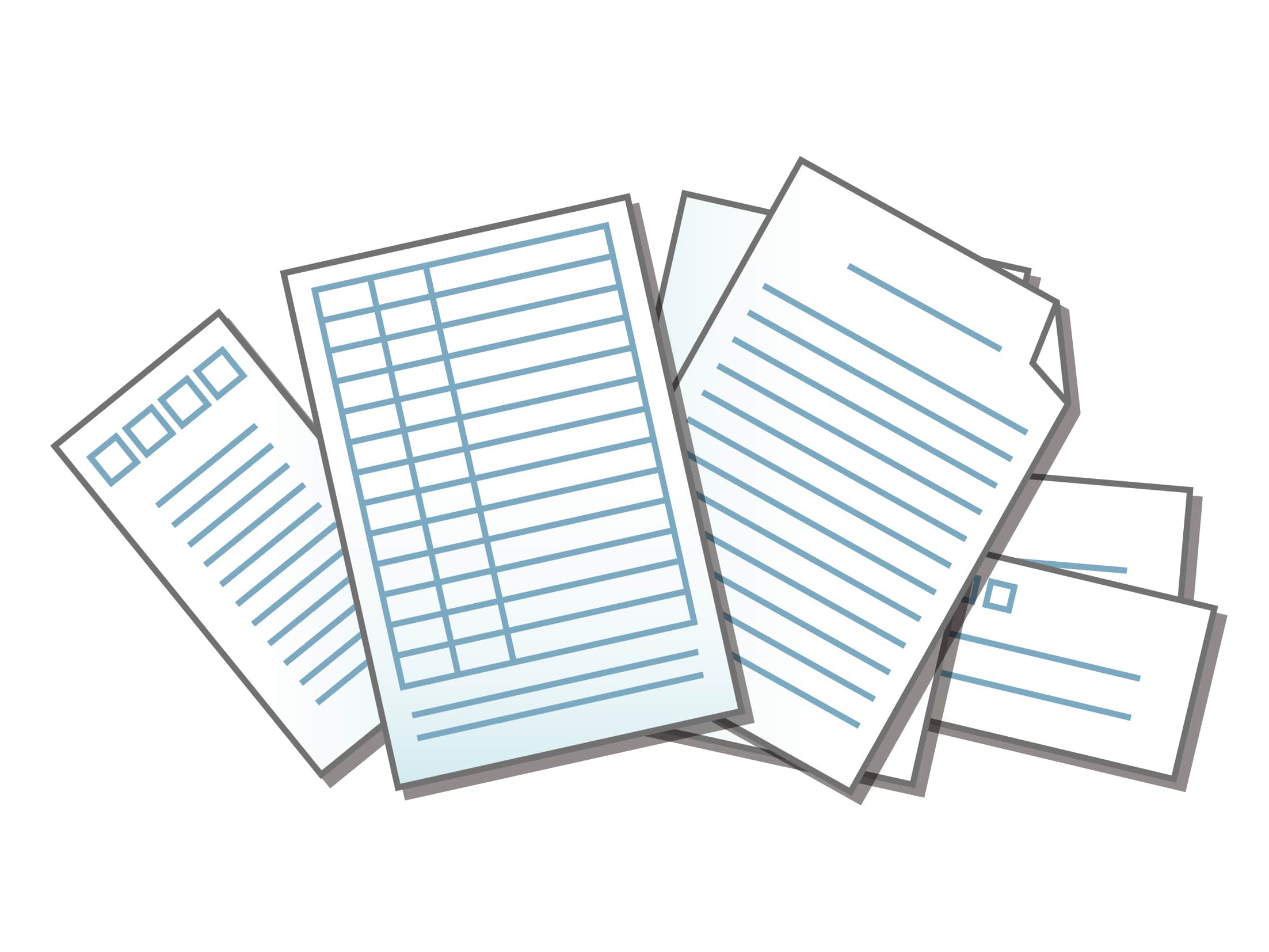
売主・買主双方の条件が合意できたら、次は「売買契約」の締結です。これは法的にも非常に重要な手続きですので、慎重に進める必要があります。
4-1. 重要事項説明
契約に先立ち、不動産会社の宅地建物取引士が、買主に対して物件に関する重要な情報を説明します。これを「重要事項説明」と言います。物件の権利関係、法令上の制限、インフラ(水道・ガス・電気)の状況、マンションの場合は管理規約や修繕積立金の状況など、多岐にわたる専門的な内容です。売主様も同席することが多いですが、内容をしっかり理解し、もし説明内容に誤りや漏れがあれば指摘する必要があります。「よくわからない」と聞き流さず、疑問点は必ずその場で確認しましょう。
4-2. 売買契約書の確認と署名・捺印
重要事項説明が終わると、「売買契約書」の読み合わせと署名・捺印に移ります。契約書には、売買代金、支払い方法、手付金の額、引き渡し時期、所有権移転の時期、契約不適合責任(昔でいう瑕疵担保責任)の期間、そして万が一契約を解除する場合の条件(違約金など)といった、非常に重要な取り決めが記載されています。
事前に合意した内容と相違ないか、不利な条件になっていないか、ご自身の目でしっかり確認してください。特に手付金の額や契約解除に関する条項は、トラブルになりやすいポイントなので要注意です。すべて納得した上で、署名・捺印を行います。
4-3. 手付金の受領
契約締結と同時に、買主から売主へ「手付金」が支払われます(通常は売買代金の5%〜10%程度)。これは契約が成立した証となるお金で、原則として現金または小切手で授受されます。領収書を発行し、確かに受け取ったことを記録に残します。
【売買契約時に売主様が必要な主な書類・持ち物】
| 書類・持ち物 | 備考 |
|---|---|
| 権利証 または 登記識別情報通知書 | 物件の所有者であることを証明する最も重要な書類。 |
| 実印 | 契約書への捺印に使用。 |
| 印鑑証明書 | 発行後3ヶ月以内のもの。実印が本物であることを証明。 |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの。 |
| 固定資産税納税通知書 | 固定資産税の年額を確認するために必要。 |
| 建築確認済証・検査済証 | 建物が法規通りに建てられた証明(あれば)。 |
| 物件の図面など | 間取り図、測量図など(あれば)。 |
| (マンションの場合)管理規約・使用細則など | マンションのルールブック。 |
| 印紙代 | 売買契約書に貼る収入印紙の費用(契約金額による)。 |
| 仲介手数料の半金(※) | 契約時に半金、決済時に残金、という支払い方が一般的。 |
※必要書類は物件の種類や状況によって異なります。必ず事前に不動産会社に確認してください。
Step 5:決済・引き渡し 〜 売却の最終ゴール
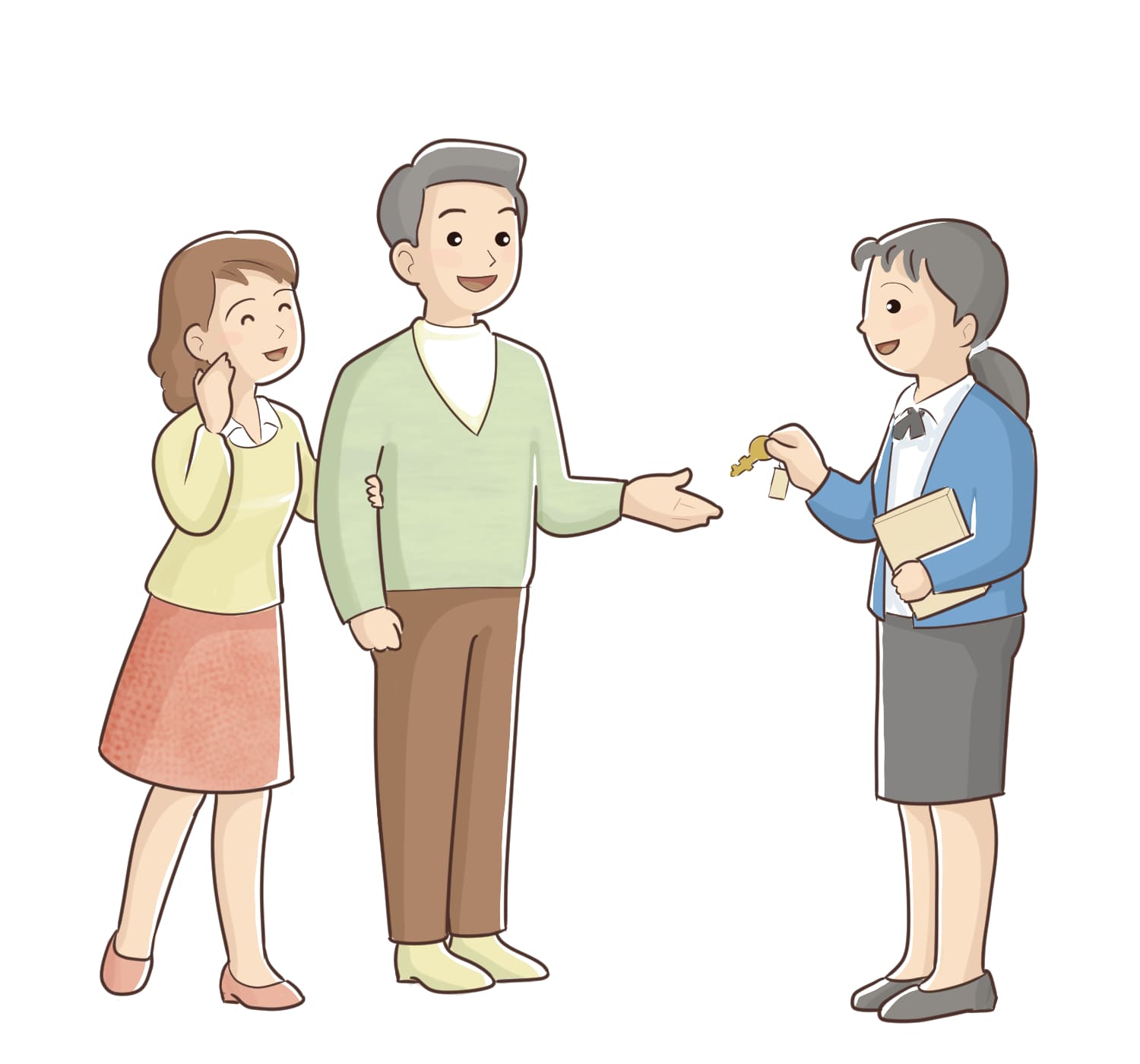
売買契約から通常1ヶ月〜2ヶ月後(契約で定めた日)、いよいよ売却の最終ステップである「決済」と「物件の引き渡し」です。
5-1. 決済当日の流れ
決済は、平日の午前中に、買主が住宅ローンを利用する金融機関の応接室などで行われるのが一般的です。売主、買主、不動産会社の担当者、そして登記手続きを代行する「司法書士」が一堂に会します。
主な流れは以下の通りです。
- 本人確認・書類確認:司法書士が売主・買主双方の本人確認と、登記に必要な書類がすべて揃っているか最終チェックを行います。
- 残代金の支払い:買主から売主の口座へ、売買代金から手付金を差し引いた「残代金」が振り込まれます。同時に、固定資産税などの日割り精算金も支払われます。
- ローン完済・抵当権抹消(※該当する場合):売主の住宅ローンが残っている場合は、この残代金の入金をもってローンを完済し、抵当権を抹消するための手続きを司法書士に依頼します。
- 諸費用の支払い:売主は、不動産会社への仲介手数料の残金や、司法書士への報酬などを支払います。
- 鍵の引き渡し:すべての支払いが完了したことを確認したら、売主は買主へ物件の鍵(スペアキー含む)をすべて引き渡します。
- 登記申請:司法書士が、その日のうちに法務局へ「所有権移転登記」と「抵当権抹消登記(該当する場合)」の申請を行います。
この一連の手続きが完了すれば、売却は無事終了です。
5-2. 物件の引き渡し
決済と同時に、物件の所有権は買主へ移ります。売主様は、引き渡し日までに、家の中を空っぽにし、簡単な清掃をしておく必要があります(契約内容によります)。電気・ガス・水道の解約手続きも忘れずに行いましょう。
引き渡し時には、買主と一緒に物件の最終確認(契約時と状態が変わっていないか、付帯設備は説明通りかなど)を行うこともあります。
【決済・引き渡し後に保管すべき書類】
売却が終わっても、関連書類は大切に保管しておきましょう。特に、翌年の確定申告で必要になります。
| 書類名 | 主な用途 |
|---|---|
| 売買契約書(原本) | 確定申告、税務調査など |
| 重要事項説明書(写し) | 契約内容の確認 |
| 物件の引渡し確認書 | 引き渡し完了の証明 |
| 登記関連書類(司法書士から後日受領) | 所有権移転の証明、確定申告 |
| 固定資産税等の精算書 | 確定申告 |
| 仲介手数料や登記費用等の領収書 | 確定申告(譲渡費用として) |
| (ローンがあった場合)住宅ローン完済証明書・抵当権抹消書類 | ローン完済の証明 |
売却後の手続き:忘れてはいけない確定申告

家を売却した「翌年」の2月16日から3月15日までの間に、税務署で「確定申告」が必要になる場合があります。
確定申告が必要なのはどんな時?
主に以下のようなケースでは、確定申告が必要です。
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 売却して「利益(譲渡所得)」が出た場合 | 利益に対して所得税・住民税がかかるため、その税額を計算・申告する必要がある。 |
| 売却して「損失」が出たが、税金の特例を使いたい場合 | 損失を他の所得と相殺できる特例(損益通算・繰越控除)を使うためには申告が必要。 |
| 利益が出ていなくても「3,000万円特別控除」などの特例を使いたい場合 | これらの特例は、申告をしないと適用されないため。(たとえ税金がゼロになる場合でも申告は必要) |
特に「3,000万円特別控除」は、売却益から最大3,000万円を差し引ける非常に大きな節税メリットですが、申告しなければゼロになってしまいます。「自分は対象になるのか?」「どう計算すればいいのか?」など、不明な点は税理士や税務署に相談するのが確実です。
確定申告に必要な主な書類
確定申告では、「家を買った時」と「家を売った時」の両方の書類が必要になります。紛失していると計算が不利になることもあるので、大切に保管しておきましょう。
| カテゴリー | 主な書類 |
|---|---|
| 取得関係(買った時) | ・購入時の売買契約書 ・購入時にかかった諸費用(仲介手数料、登記費用など)の領収書 |
| 売却関係(売った時) | ・売買契約書 ・売却時にかかった諸費用(仲介手数料、印紙代など)の領収書 ・固定資産税等の精算書 |
| その他 | ・譲渡所得の内訳書(申告書作成時に計算・記入) ・本人確認書類(マイナンバーカード等) ・(特例を使う場合)住民票など追加書類が必要な場合あり |
提出方法
作成した確定申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。
- e-Tax(イータックス):インターネット経由でオンライン提出。便利でおすすめ。
- 税務署へ持参:管轄の税務署の窓口へ直接提出。
- 郵送:管轄の税務署へ郵送で提出。
※申告書は提出前にコピーを取り、「控え」として必ず保管しておきましょう。後日、住宅ローンを組む際などに収入証明として必要になることがあります。
不動産売却をスムーズに進めるためのポイント
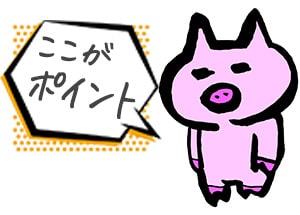
最後に、不動産売却という大きなイベントを「後悔なく」スムーズに進めるための「勘所」をまとめます。
売却活動をスムーズにするために
- 早めの情報収集と計画:「いくらで、いつまでに売りたいか」目標を明確にし、相場や流れを早めに把握。スケジュールに余裕を持つことが大切です。
- 物件の「魅力」を高める努力:内覧は第一印象が勝負。掃除・整理整頓はもちろん、必要であれば簡単な補修やハウスクリーニングも検討しましょう。
- 必要書類の事前準備:「いざという時に書類がない!」とならないよう、権利証やローン残高証明など、必要な書類は早めに確認・準備しておきましょう。
- パートナー(不動産会社)選びは慎重に:査定額だけでなく、販売戦略や担当者との相性も重視。必ず複数社を比較検討しましょう。
「専門家」の力を積極的に活用する
不動産売却には、法律や税金など、専門的な知識が不可欠な場面がたくさんあります。一人で抱え込まず、プロの力を借りるのが賢明です。
- 不動産会社:物件調査、価格査定、販売活動、契約交渉まで、売却全体のパートナー。密に連携を取り、状況を共有しましょう。
- 司法書士:登記手続き(所有権移転、抵当権抹消)の専門家。権利関係の確認も依頼できます。
- 税理士:確定申告、税金の計算、節税対策(特例の適用)の相談相手。売却後の税金についても事前に相談しておくと安心です。
- 金融機関:住宅ローンが残っている場合の返済計画や、売却後の資金計画について相談できます。
💡 成功のための最終チェックリスト
ご自身の「軸」がブレないよう、以下の点を確認しておきましょう。
- 売却の「目的」と「希望価格(最低ライン)」は明確か?
- 「いつまでに売る」というスケジュール感はあるか?
- 必要な書類は、余裕を持って準備できている(できそう)か?
- パートナー(不動産会社)との意思疎通は取れているか?
- 専門家(司法書士・税理士)に聞くべきことはないか?
- 少しでも「わからないこと」を、そのままにしていないか?