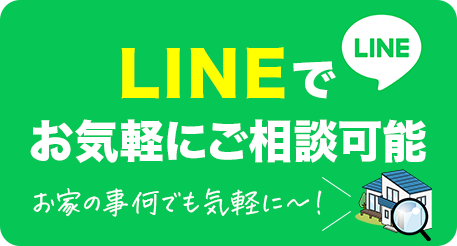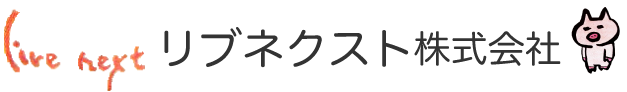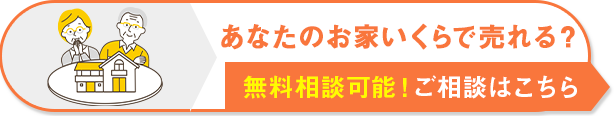不動産の相続登記にかかる費用を徹底解説|相場、内訳、節約方法

監修者
山内康司
TikTokにて、不動産売却・購入について配信中。
不動歴10年以上。元警察官。

Contents
不動産の相続登記にかかる費用を徹底解説|相場、内訳、節約方法
「実家の名義変更、まだしてないけど大丈夫かな?」
「2024年から義務化って聞いたけど、費用はいくらかかるの?」
「司法書士に頼むと高いの?自分でできる?」
親御さんが亡くなり、実家などの不動産を相続することになったとき、多くの方が直面するのが「相続登記(名義変更)」の壁です。
これまで「いつかやればいいや」と後回しにされがちだったこの手続きですが、2024年4月1日から義務化され、放置すると罰則(過料)の対象になる可能性も出てきました。
しかし、焦る必要はありません。費用がかかると言っても、その内訳を正しく理解し、適切な方法を選べば、賢く節約することも可能です。
この記事では、相続不動産の売却に関する実務経験が豊富な私たちが、相続登記にかかる費用の「リアルな相場」、意外と知られていない「節約術」、そして「専門家に頼むべきかどうかの判断基準」まで、包み隠さず解説します。
難しい法律用語はできるだけ使わず、分かりやすくお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。
相続登記とは?なぜ今、「義務化」されたのか

まずは基礎知識から。「なぜやらなきゃいけないの?」という疑問を解消しましょう。
相続登記=「不動産の所有者」を公にする手続き
相続登記とは、簡単に言えば「亡くなった方の名義になっている不動産を、相続した人の名義に変えること」です。
これをしないと、法務局の記録(登記簿)はずっと亡くなった方の名前のまま。つまり、外から見たら「誰が今の持ち主か分からない状態」になってしまいます。
これでは、いざその不動産を売りたい、と思ったときに、手続きが進められません。
そうなると、不動産の流通が悪くなって、結果活用されない不動産が増えるという悪循環になってしまいます。流通が悪くなると、全体的に不動産の値段も下がりがちなので、みんなが損してしまう形になりかねません。
2024年4月義務化スタート!放置するリスクとは?
これまで相続登記は任意でしたが、2024年4月1日から法律で義務化されました。
その背景には、全国で「所有者不明土地」が増え続け、復興事業や公共事業の妨げになるなどの深刻な問題があります。
【義務化のポイント】
- いつまでに?
不動産を相続したことを知った日から3年以内。 - もし守らないと?
正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「罰則があるから仕方なく」ではなく、「大切な資産を将来のトラブルから守るため」に、早めに済ませておくのが賢明です。
相続自体に争いがなく、誰が相続するのか決まっている場合は、はやめに相続登記しておくことをおすすめます。
相続登記にかかる費用の「内訳」を全解剖

「結局、いくら用意すればいいの?」
相続登記の費用は、大きく分けて3つあります。
- 登録免許税(必ずかかる税金)
- 必要書類の取得費用(必ずかかる実費)
- 司法書士報酬(専門家に頼む場合のみ)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
【費用1】登録免許税(必ずかかる)
これが費用の大部分を占めるケースが多いです。国に納める税金で、自分で手続きしても必ずかかります。
・計算式: 固定資産税評価額 × 0.4%
【計算例】
実家の評価額が1,000万円の場合
1,000万円 × 0.4% = 4万円
※評価額は、毎年春頃に届く「固定資産税納税通知書」で確認できます。
【ここがポイント!】免税措置を見逃すな
一定の条件(例:相続する土地の価格が100万円以下の場合など)を満たせば、この登録免許税が非課税(0円)になる特例措置があります。これを知らずに払ってしまうのはもったいないので、必ず確認しましょう。(※特例は期限付きのものが多いので、最新情報の確認が必要です)
司法書士に依頼すればそのあたりもきちっとしてくれる先生が多いです。自分で調べるのって面倒ですよね。
【費用2】必要書類の取得費用(実費)
戸籍謄本などを役所で集めるための費用です。相続人の人数や、本籍地の数によって変動しますが、数千円〜2万円程度が目安です。
被相続人の方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得して、その内容をみて相続人を特定するという作業が必要になります。本籍地がずっと同じ方であれば、比較的取りやすいですが、本籍地がかわるなどあれば手間がかかるかもしれません。
| 書類名 | 取得場所 | 費用の目安(1通あたり) |
|---|---|---|
| 戸籍謄本(現在) | 本籍地の市区町村役場 | 450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 本籍地の市区町村役場 | 750円 |
| 住民票 | 住所地の市区町村役場 | 300円 |
| 印鑑証明書 | 住所地の市区町村役場 | 300円 |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の役所 | 300〜400円 |
この金額はあくまでも目安です。発行する主体によって金額がちがっていますのでお気をつけください。
【費用3】司法書士報酬(専門家に頼む場合)
手続きを司法書士に丸投げする場合にかかる費用です。
事務所によって料金は自由ですが、一般的な相場は以下の通りです。
司法書士は、遺産分割協議書を作成していくことが大きな業務です。
相続人全ての人の署名押印と印鑑証明などが必要となってきます。
とくに、外国籍がの方がいらっしゃる場合は、手続きが煩雑になりますので、司法書士のなかでも、得意不得意が出てくる領域です。
・相場目安: 6万円 〜 15万円程度
あくまでも目安の金額です。
※物件の数が多い、相続人が多くて揉めている、古い戸籍を集めるのが大変、といった複雑なケースでは追加料金がかかることもあります。
少しでも安く!相続登記の費用を抑える3つの方法

「できるだけ出費は抑えたい」というのが本音ですよね。プロが教える節約術をご紹介します。
【節約術1】自分で手続きに挑戦してみる
最大の節約方法は、司法書士報酬(6〜15万円)をカットすること、つまり「自分でやる」ことです。
今は法務局のホームページに申請書の様式や記載例が充実していますし、事前予約制の登記相談窓口もあります。
【自分でできる人の特徴】
- 平日の日中に時間が取れる(役所や法務局は平日のみ)
- 相続人が少なく、話し合いがまとまっている
- パソコンでの書類作成に慣れている
- 根気強く、細かい作業が苦にならない
逆に、「忙しい」「相続関係が複雑」「絶対にミスしたくない」という方は、無理せず専門家を頼る方が、時間と精神的なコストを考えると「安い」かもしれません。
【節約術2】「書類集め」だけ自分でやる
司法書士に依頼する場合でも、「戸籍謄本などの収集は自分たちでやります」と伝えれば、その分の手数料(数万円程度)を値引きしてくれる事務所もあります。
ただし、古い戸籍を遡って全て集めるのは、想像以上に大変な作業になることも…。どこまで自分でやるか、事前に司法書士と相談してみましょう。
【節約術3】複数の事務所で「相見積もり」を取る
司法書士報酬は自由化されており、事務所によって料金設定が全く違います。
「A事務所は10万円だったけど、B事務所は7万円だった」ということも珍しくありません。
最初から1社に絞らず、2〜3社に問い合わせて見積もりを取り、料金だけでなく、対応の丁寧さや説明の分かりやすさも比較して選ぶことをお勧めします。
私たちリブネクストが考える「相続登記」の真の価値

単なる「事務手続き」として片付けてしまうのは、少しもったいないかもしれません。
私たちは、相続登記を「資産の健康診断」の機会だと考えています。
「とりあえず名義変更」の落とし穴
「義務化されたから、とりあえず長男の名義にしておこう」
ちょっと待ってください。その判断、将来の二次相続や、売却時の税金のことまで考えていますか?
一度名義を決めて登記してしまうと、後から簡単に変えることはできません(贈与税などがかかる可能性があります)。
「誰の名義にするのが、家族全体にとって一番メリットがあるか?」を、この機会にしっかり話し合うことが大切です。
実際に過去、適当に相続登記したな、、、というので売却が困難になったり、場合によっては価値を下げてしまったこともあります。
そんな名義の違いで価値さがるの???って思われるかもしれません。
たとえば、3人相続人がいるから3人の共有にしようとした場合、3人相続人がいるから土地を3つにわけて相続登記した場合など、かなりリスクがあります。
売却を見据えた「戦略的」な相続登記
もし将来的に「売却」を考えているなら、相続登記の段階から準備が必要です。
例えば、売却時に使える「3,000万円特別控除」などの特例は、誰が相続するかによって使えるかどうかが変わります。
私たちは不動産のプロとして、「その後の活用や売却まで見据えた、最適な相続の形」を考え、その上で、もっともよい相続の形を整えます。
まとめ:不安なら、まずは専門家の「無料相談」へ
相続登記は、2024年の義務化により、避けては通れない道となりました。
費用は、自分で行えば数万円(実費のみ)、専門家に頼めばプラス10万円前後が目安です。
「費用を節約して自分で頑張る」のも一つの選択肢ですが、時間や手間、将来のリスクを考えると、「プロに任せて安心を買う」のも賢い選択と言えるでしょう。
問題はプロに任せるべきか、本人で行うべきかの判断です。簡単な登記で、相続人同士で争いがない場合、本人でも可能です。
節約することが、その人にとってよいかどうか、一緒に考えていきましょう。
大切なのは、放置せずに一歩を踏み出すことです。
「我が家の場合はいくらかかりそう?」「何から手を付ければいい?」
そんな疑問があれば、まずは司法書士や不動産の専門家が行っている「無料相談」を活用してみてはいかがでしょうか。