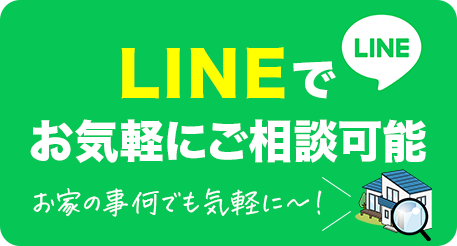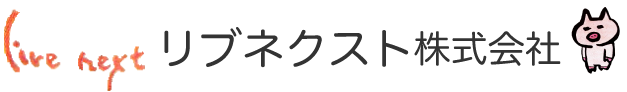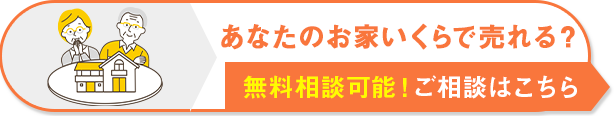家の売却における残置物問題:スムーズな売却のための完全ガイド

監修者
山内康司
TikTokにて、不動産売却・購入について配信中。
不動歴10年以上。元警察官。

Contents
【家の売却 残置物 完全ガイド】処分方法は?費用は?トラブルなくスムーズに売るための全知識!
「家を売りたいけど、家の中の荷物、どうしよう…」「家具とか家電、全部持っていくのは大変だし、捨てるのもお金がかかりそう…」「残したままだと売れないの?」
家の売却を考え始めた時、意外と大きな悩みとなるのが、この「残置物(ざんちぶつ)」の問題。特に、長年住んだ家や相続した実家の場合、家財道具が大量に残っていて、途方に暮れてしまう方も少なくありません。
残置物の扱いは、売却をスムーズに進めるため、そして後々のトラブルを避けるために、非常に重要なポイントです。
この記事では、そんな残置物問題でお悩みのあなたのために、「そもそも残置物って何?」という基本から、具体的な処分方法(自分でやる?業者に頼む?)、気になる費用相場と節約のコツ、そして売却時に絶対に注意すべき点まで、残置物に関するあらゆる情報を網羅的に、分かりやすく解説します! この記事を読めば、残置物に関する不安が解消され、安心して家の売却を進められるはずです。
そもそも「残置物」って何? 売却時の基本ルール

まずは基本から。「残置物」とは何か、誰のものなのか、売却時にどう扱われるのか、しっかり理解しておきましょう。
残置物の定義:「置いていかれるモノ」のこと
残置物とは、簡単に言うと、家を売却して引き渡す際に、売主(前の住人)が家の中に残していく私物(動産)のことです。
【残置物になる可能性のあるモノ(例)】
| カテゴリー | 具体例 |
|---|---|
| 家具類 | ソファ、ベッド、タンス、食器棚、テーブル、椅子、本棚、テレビ台 など |
| 家電製品 | 冷蔵庫、洗濯機、テレビ、電子レンジ、炊飯器、掃除機、扇風機 など ※エアコン、照明器具は、取り外し可能なら残置物扱いになることも多いが、物件設備として引き渡すか要確認。 |
| 日用品・雑貨 | 食器、調理器具、寝具、衣類、書籍、おもちゃ、置物 など |
| 趣味の道具 | スポーツ用品、楽器、コレクション品 など |
| その他 | 自転車、物置、庭の植木鉢や置物、ゴミ など |
【残置物にならないモノ(原則)】
一方で、建物に固定されていて、通常は物件の一部(設備)として扱われるものは、残置物とはみなされません。
- 作り付けの棚や収納
- システムキッチン、ユニットバス
- 壁に取り付けられたエアコン(※契約による場合あり)
- 天井に直接取り付けられた照明器具(※契約による場合あり)
ただし、この線引きは法律で明確に決まっているわけではなく、特にエアコンや照明器具などは、売主と買主の認識がずれやすく、トラブルの原因になりがちです。だからこそ、契約前に「何を残し、何を撤去するか」をしっかり話し合い、書面で確認することが非常に重要になります。
残置物の所有権は誰に? 原則は「売主」の責任で処分!
家の中にある残置物の所有権は、引き渡しが完了するまでは、当然ながら売主にあります。
そして、不動産売買の原則は「空渡し(からわたし)」。つまり、売主は、特別な合意がない限り、引き渡し日までに全ての残置物を撤去し、家の中を空っぽの状態にして買主に引き渡す義務を負います。
もし、売主が残置物を撤去せずに引き渡してしまった場合、買主から撤去費用を請求されたり、契約不履行として損害賠償を求められたりする可能性もあります。
ただし、例外として、
- 買主が「この家具やエアコンは、まだ使えるから置いていってほしい」と希望し、売主もそれに合意した場合
- 売買契約の特約で「残置物がある状態で引き渡す(現状有姿渡し)」と明確に定めた場合
などは、残置物を残したまま引き渡すことも可能です。この場合、引き渡しと同時に残置物の所有権も買主に移転するのが一般的です。しかし、この場合も、どの物を残すのか、その状態はどうなのかを、契約前にしっかり確認し、書面に残しておくことがトラブル回避の鍵となります。
どうやって処分する? 残置物処分の【3つの方法】を比較!

「原則、売主が処分」となると、気になるのはその方法と費用ですよね。主な処分方法は3つあります。
| 処分方法 | メリット | デメリット/注意点 | どんな人向け? |
|---|---|---|---|
| ① 自分で処分する (自治体ゴミ、リサイクル、フリマなど) |
・費用を最も安く抑えられる可能性がある。 ・売れるものは収入になることも。 |
・時間と手間が非常にかかる! ・分別ルールが細かい(粗大ゴミ、家電リサイクル法など)。 ・運搬手段(車など)が必要な場合も。 ・量が多すぎると現実的でない。 |
・時間に余裕がある人。 ・体力に自信がある人。 ・残置物の量が比較的少ない人。 ・少しでも費用を節約したい人。 |
| ② 専門業者に依頼する (不用品回収業者、遺品整理業者など) |
・手間がかからない! 分別・搬出・処分まで全て任せられる。 ・短時間で片付く。 ・買取可能な業者なら、費用と相殺できることも。 |
・費用がかかる(量や内容によるが、数万~数十万円以上も)。 ・悪質な業者に注意が必要!(高額請求、不法投棄など)。 ・業者選び(相見積もり)に手間がかかる。 |
・時間がない、忙しい人。 ・残置物の量が多い人。 ・遠方に住んでいて自分で片付けられない人。 ・体力的に難しい人。 |
| ③ 不動産会社に相談・依頼する | ・売却活動と並行して処分を進められる。 ・提携している信頼できる処分業者を紹介してもらえることが多い。 ・買取オプションがある会社なら、残置物ごと家を買い取ってもらえる可能性も。 |
・仲介手数料とは別に処分費用がかかる。 ・会社によっては対応していない、または割高になる可能性も。 ・買取の場合は、売却価格が安くなる。 |
・売却と処分をワンストップで済ませたい人。 ・自分で業者を探すのが面倒な人。 ・買取も視野に入れている人。 |
方法①:自分で処分する場合 ~費用は安いが、時間と労力が…
最も費用を抑えられる可能性があるのが、自分でコツコツ処分する方法です。
- まずは仕分け:「捨てる物」「売る物(リサイクル)」「譲る物」に分けます。
- 捨てる:
- 燃えるゴミ・燃えないゴミ → 自治体のルールに従って出す。
- 粗大ゴミ → 自治体に申し込み、料金を支払い、指定場所に出す(または自分で処理施設へ持ち込む)。
- 家電リサイクル法対象品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)→ 購入店または自治体が指定する方法でリサイクル料金を支払い処分。
- 売る・譲る:
- リサイクルショップへ持ち込む/出張買取を依頼する。
- フリマアプリ(メルカリなど)やネットオークションに出品する。
- 友人・知人・地域の掲示板(ジモティーなど)で譲る相手を探す。
メリットは費用節約と、売れれば収入になる点。デメリットは、とにかく時間と手間がかかること! 特に実家一軒まるごととなると、数週間~数ヶ月かかることも覚悟が必要です。自治体のゴミ出しルールや粗大ゴミの予約方法なども事前にしっかり確認しましょう。
方法②:専門業者に依頼する場合 ~お金はかかるが、ラクで早い!
「時間がない」「量が多すぎる」「体力的に無理」…そんな場合は、プロの不用品回収業者や遺品整理業者に任せるのが現実的です。
- 業者を探す:ネット検索や、不動産会社からの紹介などで候補を探す。
- 相見積もりを取る:必ず複数の業者(最低3社)に見積もりを依頼する! 電話だけでなく、可能なら現地訪問してもらって正確な量を見てもらうのがベスト。
- 見積もり内容を比較検討:総額だけでなく、作業内容(分別、搬出、清掃)、追加料金の有無、作業日時などをしっかり比較する。
- 業者を決定し、契約する:契約書の内容(特に料金と作業範囲)をよく確認する。
- 作業当日:立ち会いが必要な場合が多い。作業完了後に最終確認。
メリットは、圧倒的な「ラクさ」と「スピード」。デメリットは「費用」です。 そして、最も注意すべきは「悪質業者」の存在。「無料回収」をうたって後で高額請求されたり、回収した物を不法投棄されたりするトラブルも。「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持っているか、所在地や連絡先が明確か、見積もりは書面でくれるか、などをしっかり確認し、信頼できる業者を選びましょう。
方法③:不動産会社に相談する場合 ~売却とセットで解決も?
家の売却を依頼する不動産会社に、残置物処分の相談をしてみるのも良い方法です。
- 処分業者の紹介:多くの不動産会社は、提携している信頼できる処分業者を知っています。自分で探す手間が省け、相場より安く依頼できる可能性も。
- 処分費用の立て替え・売却代金からの精算:手元に処分費用がない場合、一時的に立て替えてくれたり、売却代金から差し引いて精算してくれたりする会社もあります。(要相談)
- 買取オプション:「残置物ごと、そのままの状態で家を買い取ります」という「買取」サービスを提供している不動産会社もあります。売却価格は仲介より安くなりますが、処分費用も手間も一切かからず、すぐに現金化できるという大きなメリットがあります。
特に、相続した実家が遠方にある場合や、すぐに現金化したい場合には、不動産会社に処分も含めて相談・依頼するのが、最もスムーズで現実的な解決策になることが多いです。私たちリブネクストも、お客様の状況に合わせて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
気になる!残置物処分費用の目安と節約のコツ

専門業者に依頼する場合、費用はどれくらいかかるのでしょうか? あくまで目安ですが、知っておくと予算が立てやすくなります。
費用の決まり方:量と内容、作業の手間がポイント
業者に依頼した場合の費用は、主に以下の要素で決まります。
- 残置物の「量」:単純に物量が多ければ多いほど高くなります。(トラックの台数や大きさで料金が決まることが多い)
- 残置物の「種類」:処分に手間や費用がかかる物(例:家電リサイクル品、ピアノ、金庫など)が多いと高くなる傾向。
- 作業員の「人数」と「時間」:搬出経路が複雑(階段しかない、道が狭いなど)で時間がかかる場合は高くなることも。
- オプション作業:ハウスクリーニング、エアコン取り外し、物置解体などを追加で依頼すれば、その分費用が加算されます。
間取り別 費用相場(あくまで目安!)
業者や地域、物の量によって大きく異なりますが、一般的な「家一軒まるごと片付け」の場合の費用相場イメージです。
| 間取り | 作業員目安 | トラック目安 | 費用相場(目安) |
|---|---|---|---|
| 1K / 1DK | 1~2名 | 軽トラック~1tトラック | 3万円 ~ 8万円程度 |
| 1LDK / 2DK | 2~3名 | 1.5t~2tトラック | 7万円 ~ 15万円程度 |
| 2LDK / 3DK | 3~4名 | 2t~3tトラック | 12万円 ~ 25万円程度 |
| 3LDK / 4DK | 3~5名 | 3t~4tトラック | 18万円 ~ 35万円程度 |
| 4LDK~ / 一軒家 | 4名~ | 4tトラック以上 | 25万円 ~ 60万円以上 (物の量により大きく変動) |
※上記はあくまで一般的な目安です。遺品整理などで特殊な作業が必要な場合や、ゴミ屋敷状態の場合は、さらに高額になる可能性があります。必ず複数の業者から見積もりを取りましょう。
費用を少しでも抑える!節約のコツ
高額になりがちな処分費用。少しでも安く抑えるためには、こんな工夫が考えられます。
- 【最重要】必ず「相見積もり」を取る!:業者によって料金設定はバラバラ。最低3社は比較しましょう。
- 自分でできることは自分でやる:事前にゴミ袋に入るような細かい物を分別・処分しておくだけでも、業者の作業量が減り、安くなる可能性があります。
- 買取可能な業者を選ぶ:まだ使える家具や家電、骨董品などを買い取ってくれる業者なら、処分費用と相殺できる可能性があります。(ただし、買取価格に過度な期待は禁物)
- 繁忙期を避ける:引越しシーズン(3~4月)などは業者が忙しく、料金が高くなる傾向があります。可能であれば時期をずらす。
- 料金プランを確認する:「トラック積み放題プラン」など、定額プランがお得な場合もあります。(ただし、諸条件をよく確認!)
残置物ありで売却する際の【超重要】注意点:トラブル回避のために!
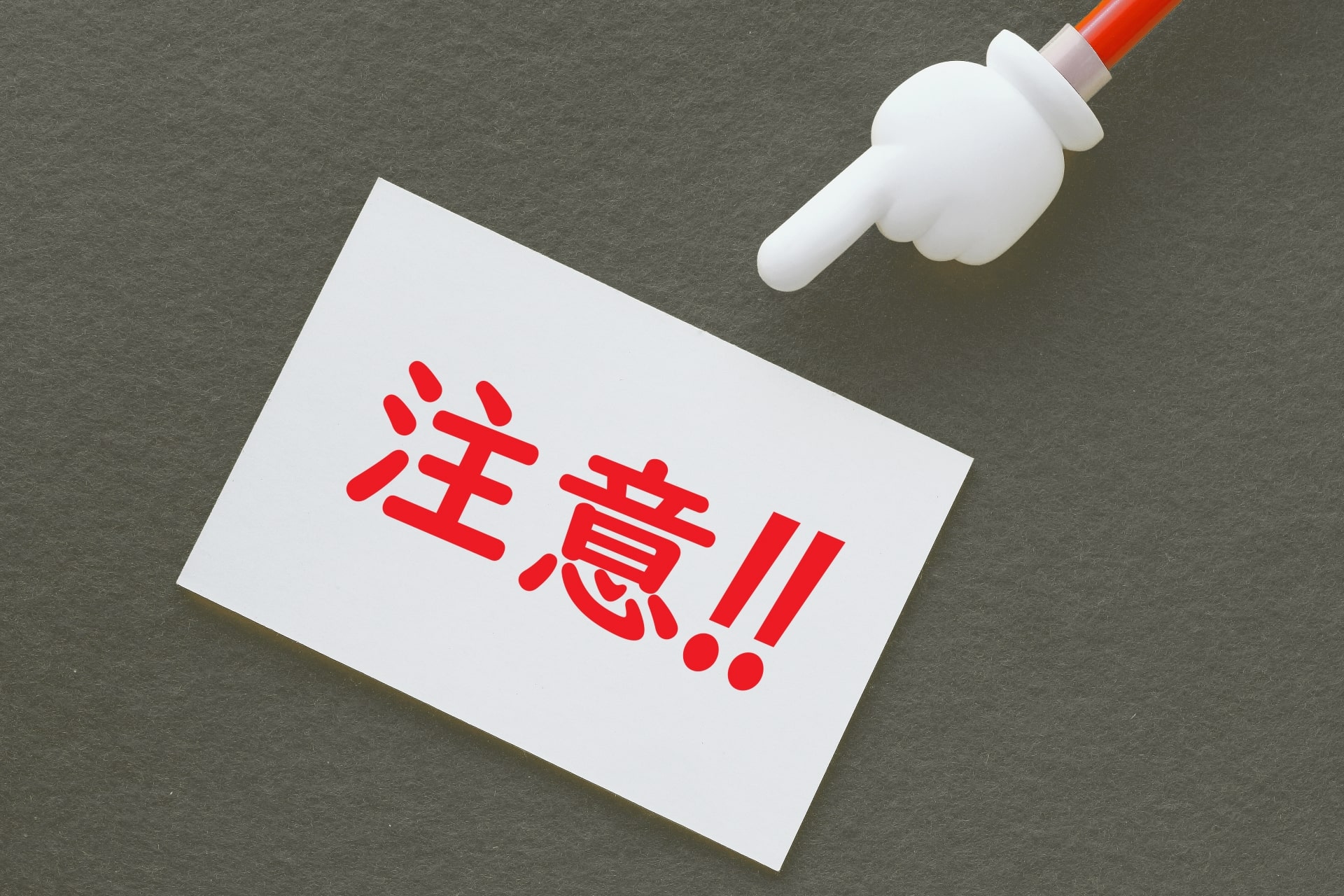
「買主さんが『そのままでいい』って言ったから…」と安易に残置物を残して引き渡すと、後で大きなトラブルになることも! 残置物ありで売却する場合は、以下の点に細心の注意を払いましょう。
| # | 注意点 | 具体的なアクション |
|---|---|---|
| ① | 【必須】契約書に 必ず明記する! |
・「どの」残置物を「どのような状態」で引き渡すのか、具体的にリスト化し、売買契約書や「付帯設備表」に添付・明記する。 ・残置物の所有権が「引き渡しをもって買主に移転する」旨も記載。 ・エアコンや照明など、設備なのか残置物なのか曖昧なものは、特に明確に記載する。 ★口約束は絶対にNG! |
| ② | 買主への 丁寧な説明 |
・リストや写真を使って、残す物の種類、量、そして「状態」(傷や汚れ、故障の有無など)を、契約前に買主にしっかり説明し、納得してもらう。 ・特に故障している物や使用できない物を残す場合は、その旨を明確に伝える。(後で「聞いてない!」となるのを防ぐ) |
| ③ | 「ゴミ」は 絶対にNG! |
・いくら「現状有姿」で合意していても、明らかなゴミ(生活ゴミ、粗大ゴミなど)を残していくのは契約違反とみなされる可能性が高い。 ・最低限、ゴミの処分は売主の責任で行う。 |
| ④ | 引き渡し前の 最終確認 |
・引き渡し前に、買主と一緒に、契約書(付帯設備表)に記載された通りの物が残され、それ以外の物が撤去されているか、最終確認を行うのが望ましい。 |
| ⑤ | 不安な場合は 専門家を頼る |
・残置物の量が多い、価値のある物が含まれる、買主との合意形成が難しい…など、少しでも不安があれば、不動産会社や弁護士に相談する。 |
残置物の取り扱いは、売却後のトラブル原因として非常に多い項目です。「言った・言わない」を防ぐために、必ず書面で明確な合意を残すこと! これが鉄則です。
まとめ:残置物問題は早めの計画と適切な対応でクリア!
家の売却における残置物問題。処分には時間も手間も費用もかかり、頭の痛い問題ですが、避けては通れません。
大切なのは、
- 売却活動の早い段階から、残置物をどうするか計画を立て始めること。
- 自分に合った処分方法(自分でやる or 業者 or 不動産会社相談)を選ぶこと。
- 業者に頼む場合は、必ず相見積もりを取り、信頼できる業者を選ぶこと。
- 残置物ありで売却する場合は、契約書での取り決めと買主への説明を徹底すること。
これらのポイントを押さえておけば、残置物に関する不安やトラブルを最小限に抑え、スムーズな売却を実現できるはずです。
面倒な残置物の処分も含めて、家の売却を安心して任せたい…そんな時は、ぜひ私たちにご相談ください。
尼崎での実家売却、残置物処分も「リブネクスト」にお任せ!
家の売却後のリスクを極力無くしたい方、特に残置物の処分にお困りの方は、ぜひ「リブネクスト」にお気軽にご相談ください。
私たちは、お客様の状況に合わせて、最適な処分方法のご提案や、信頼できる専門業者のご紹介、さらには残置物ごと現状のまま買い取る「買取サービス」もご提供可能です。
尼崎市での豊富な売却実績を持つ「リブネクスト」が、あなたの負担を軽減し、スムーズな売却を全力でサポートします!
→ リブネクストが不動産売却で選ばれている理由はこちら
お問い合わせフォーム・お電話・LINEから、あなたに合った方法でご連絡いただけます! まずは無料相談から。