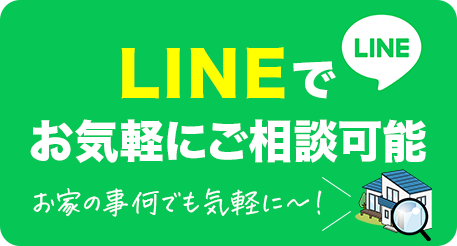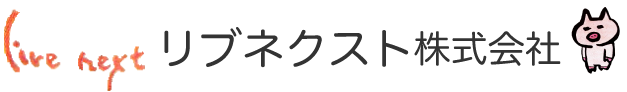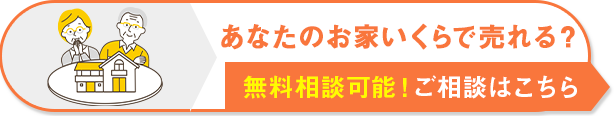家を売却した時の譲渡所得税とは?計算方法から節税対策まで徹底解説

監修者
山内康司
TikTokにて、不動産売却・購入について配信中。
不動歴10年以上。元警察官。

Contents
【家売却の税金】譲渡所得税はいくら?計算方法から最強の節税対策、確定申告まで徹底ガイド!
「家を売却したら、税金ってどれくらいかかるんだろう…」「譲渡所得税って聞いたけど、計算方法がわからない…」「できるだけ税金を安くする方法はないの?」
家を売却して利益が出た場合、避けては通れないのが「譲渡所得税」の問題。金額も大きくなりがちで、多くの方が不安に感じるポイントですよね。でも、仕組みをちゃんと理解して、使える制度を賢く活用すれば、必要以上に恐れることはありません!
この記事では、不動産売却にかかる譲渡所得税について、「そもそも何なのか?」という基本から、具体的な計算方法、そして知らなきゃ大損する可能性のある「節税対策(控除・特例)」、さらには売却後の確定申告の手順まで、あなたが損をしないために知っておくべき情報を、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します! 税金の不安を解消して、賢く不動産売却を進めましょう。
そもそも「譲渡所得税」って何? なぜかかるの?

まずは基本のキから。家を売った時にかかる税金について、正しく理解しておきましょう。
「利益(譲渡所得)」に対してかかる税金です
家や土地などの不動産を売却して得た利益のことを「譲渡所得(じょうとしょとく)」と言います。この譲渡所得に対してかかる税金が、いわゆる「譲渡所得税」です。(※より正確には、所得税・復興特別所得税・住民税の3つを合わせた呼び方です)
ポイントは「利益が出た場合にかかる」という点。 もし、家を買った時よりも安い値段でしか売れなかった場合(=損失が出た場合)は、基本的にこの譲渡所得税はかかりません。
この譲渡所得は、お給料などの他の所得とは分けて計算され(分離課税)、原則として家を売却した翌年に「確定申告」をして納税する必要があります。
税額を決める最重要ポイント:「譲渡所得」の計算方法
では、税金がかかるかどうかの分かれ目、そして税額の元となる「譲渡所得(利益)」は、どうやって計算するのでしょうか?
基本の計算式はこれです↓
つまり、「売れた金額」から、「買うのにかかったお金(取得費)」と「売るのにかかったお金(譲渡費用)」を差し引いたものが、課税対象となる利益(譲渡所得)になるわけです。
ここでカギとなるのが、「取得費」と「譲渡費用」に何が含まれて、それをどうやって証明するか、という点。ここを正確に計算できるかが、正しい税額を知る(そして節税する)ための超重要ポイントになります!
| 項目 | 内容・含まれるもの(主な例) | 証明書類・注意点 |
|---|---|---|
| 売却価格 | ・実際に家(土地・建物)が売れた金額。 | ・売買契約書で確認。 |
| 取得費 (超重要!) |
その家を買った(建てた)時にかかった費用のこと。多ければ多いほど税金が安くなる!
|
・購入時の売買契約書が最重要! ・購入時の諸費用の領収書 ・ローン返済予定表 ・リフォーム契約書・領収書 ・当時の通帳記録など 【取得費不明の場合のリスク】 |
| 譲渡費用 | その家を売るために「直接」かかった費用のこと。これも多いほど税金が安くなる。
|
・仲介手数料の領収書 ・登記費用の領収書 ・測量費の領収書 ・解体費用の領収書など 領収書は確定申告まで必ず保管! |
この計算で「譲渡所得」がプラスになれば、その金額に税率を掛けて税額が決まります。マイナス(譲渡損失)の場合は、原則、税金はかかりません。
特に「取得費」を証明する書類(購入時の契約書や領収書)は、税額に直結する超重要アイテムです! 家に関する書類は、普段からまとめて大切に保管しておく習慣をつけましょう。
税率が倍近く違う!?「所有期間」の重要性
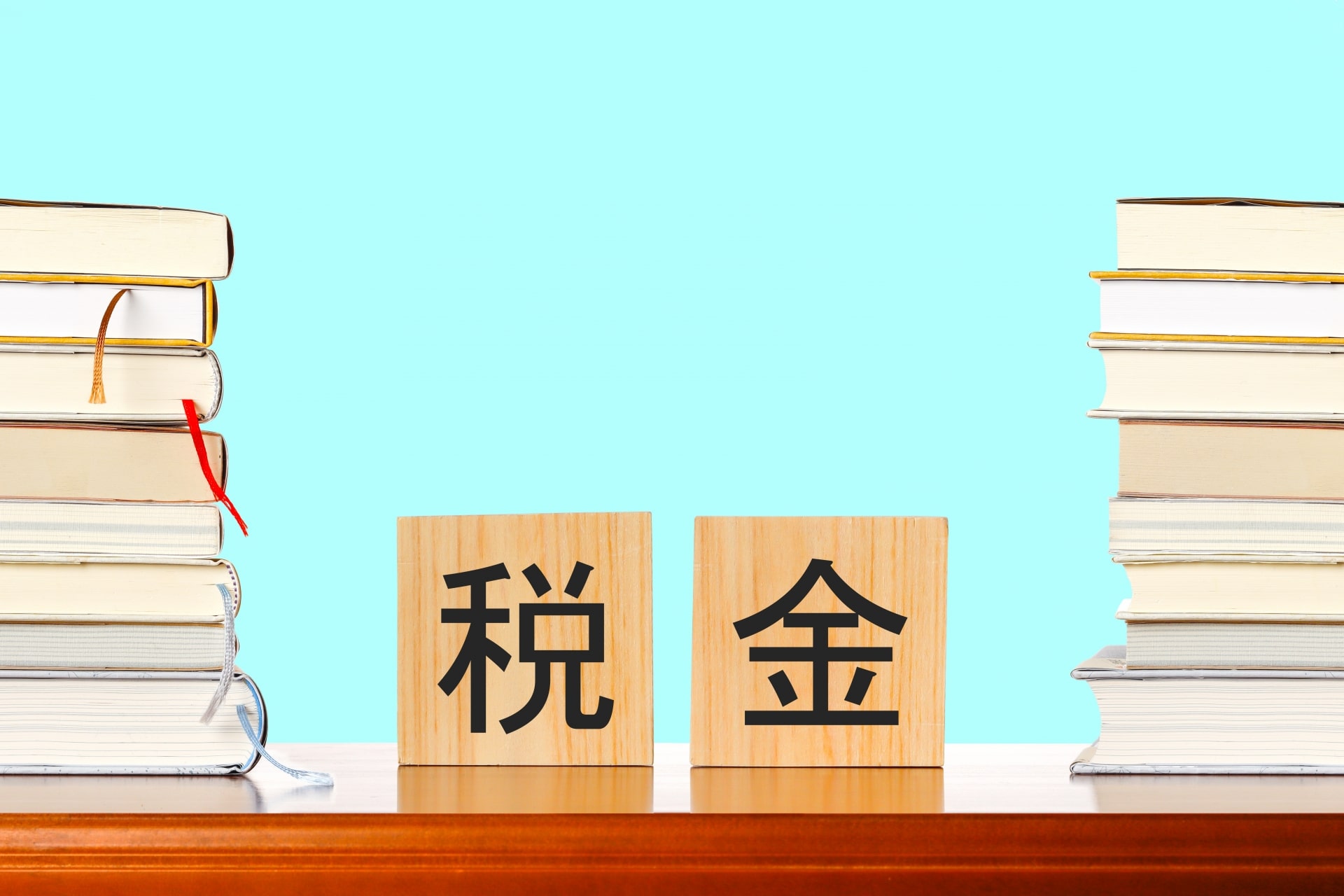
譲渡所得税の計算でもう一つ、絶対に知っておかなければならないのが「所有期間」です。なぜなら、家を所有していた期間が5年を超えるかどうかで、適用される税率が劇的に変わるからです!
| 所有期間の判定(※) | 区分 | 所得税 (復興特別所得税含む) |
住民税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 30.63% | 9% | 約 39.63% |
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 15.315% | 5% | 約 20.315% |
※【超重要!】所有期間の判定基準日
所有期間は、実際に家を売却した日ではなく、売却した年の「1月1日」時点でカウントします! 例えば、2020年4月1日に購入した家を2025年10月1日に売却した場合、実際の所有期間は5年6ヶ月ですが、2025年1月1日時点ではまだ4年9ヶ月しか経っていないため、「短期譲渡所得」の高い税率(約39.63%)が適用されてしまいます! この判定基準は非常に間違いやすく、税額に大きな影響を与えるため、絶対に注意してください。
見ての通り、税率はほぼダブルスコア! 例えば譲渡所得が1,000万円の場合、
- 短期(5年以下)だと税額は 約396万円
- 長期(5年超)だと税額は 約203万円
となり、約193万円もの差が出ます! 「あと数ヶ月待てば長期になるのに…」という場合は、売却時期を少し延期することも、非常に有効な節税対策になり得るのです。
知らないと大損!最強の節税対策「控除・特例」をフル活用しよう!

「税率20%や40%なんて高すぎる…」と感じた方も多いかもしれません。でも、ご安心ください! 特に自分が住んでいた家(マイホーム=居住用財産)の売却には、税負担を劇的に軽くできる、知らなきゃ損する強力な「控除」や「特例」がいくつも用意されています。これらを賢く使うことが、手残りを最大化する最大のポイントです!
ただし、これらの特例は自分から確定申告をしないと絶対に適用されません!
| 控除・特例の名前 | どんな制度? | 使えるのはどんな時?(主な要件) | 併用・注意点 |
|---|---|---|---|
| 【最強!】 居住用財産の 3,000万円特別控除 |
譲渡所得(利益)から最大3,000万円を差し引ける! (利益3,000万円以下なら税金ゼロ!) |
・自分が住んでいた家(または住まなくなって3年目の年末まで) ・家屋を取り壊した場合は条件あり ・親子・夫婦間など特別な関係への売却でない ・過去2年間にこの特例や買換え特例などを使っていない |
・軽減税率と併用可 ・買換え特例や住宅ローン控除(売却年とその前後2年)とは併用不可 ・確定申告必須! |
| 【併用可!】 所有期間10年超 居住用財産の軽減税率 |
利益のうち6,000万円以下の部分の税率が約14%に軽減! (長期税率約20%よりさらに低い) |
・所有期間が10年超の居住用財産(売却年の1月1日時点) ・3,000万円控除の要件も満たす必要あり |
・3,000万円控除と併用可 ・確定申告必須! |
| 【損失が出ても!】 特定のマイホームの 譲渡損失の損益通算 及び繰越控除 |
マイホーム売却の損失を他の黒字所得(給与など)と相殺(損益通算)したり、翌年以降3年間繰り越せる(繰越控除)。 → 所得税・住民税が戻ってくる! |
・所有期間が5年超の居住用財産 ・(買換えの場合)新居のローンが10年以上など ・(買換えしない場合)売却契約年の年末にローン残高があることなど |
・確定申告必須! |
| 【住み替えに】 特定の居住用財産の 買換え・交換の特例 |
売却益への課税を将来に繰り延べ(次に売る時まで先送り)できる。 (※節税ではなく課税の繰り延べ) |
・所有期間10年超、居住期間10年以上 ・売却代金1億円以下 ・新居の面積・価格要件あり など(要件複雑) |
・3,000万円控除や軽減税率とは併用不可(選択適用) ・確定申告必須! |
| 【相続した家に】 被相続人の居住用財産 (空き家)の特別控除 |
相続した空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円控除。 | ・相続開始から3年目の年末までに売却 ・耐震リフォーム or 家解体 ・相続前に被相続人一人暮らし など(要件非常に細かい!) |
・確定申告必須! |
【最重要注意点】どの特例を使うのが一番有利かは、あなたの状況によって全く異なります! 特に「3,000万円控除」と「買換え特例」「住宅ローン控除」のどれを選ぶかは、税額に大きな影響を与えます。必ず税理士などの専門家に相談して、シミュレーションしてもらうことを強く推奨します。
これらの特例を知っているか知らないかで、手元に残るお金が文字通り「数百万円」変わることも珍しくありません。面倒くさがらずに、しっかり調べて活用しましょう!
最終関門!「確定申告」の手順と必要書類

譲渡所得税の計算ができ、使う特例も決まったら、いよいよ最終ステップ「確定申告」です。売却した翌年の2月16日から3月15日までに、税務署へ申告と納税(または還付申請)を行います。
ステップ1:必要書類をかき集める!
確定申告で一番時間がかかる&重要なのが、この「書類集め」です。売却に関する書類はもちろん、「買った時」の書類も必要になります。
| カテゴリー | 主な書類 | 入手先・備考 |
|---|---|---|
| 売却関係 | 売買契約書のコピー | ご自身で保管 |
| 譲渡費用の領収書(仲介手数料、印紙代、登記費用など) | 不動産会社、司法書士などから受領、ご自身で保管(★無くさない!) | |
| 固定資産税等精算書のコピー | 不動産会社から受領 | |
| 取得関係 (超重要!) |
購入時の売買契約書のコピー | ご自身で保管(★最重要書類!無ければ概算取得費で大損の可能性) |
| 購入時の諸費用の領収書 | ご自身で保管(あればあるだけ有利) | |
| 登記関係 | (売却時)全部事項証明書(登記簿謄本) | 法務局、司法書士(不動産会社が用意してくれることも) |
| 本人確認など | ・マイナンバーカード(または通知カード+身分証明書) ・銀行口座情報(還付の場合) ・印鑑 |
ご自身で用意 |
| (特例利用時) 追加書類 |
・(3000万円控除など)売却した家の戸籍の附票 or 住民票除票 ・(買換え特例)新居の売買契約書、登記事項証明書など ・(相続空き家特例)被相続人の住民票除票、耐震基準適合証明書 or 解体証明書など |
市区町村役場、不動産会社、建築士事務所など ※利用する特例によって必要書類が大きく異なります。税務署HPや税理士に要確認! |
| 申告書 | ・確定申告書B ・分離課税用の申告書(第三表) ・譲渡所得の内訳書 |
税務署、国税庁HPで作成・入手 |
※書類集めは本当に大変です! 売却が決まったらすぐに探し始めましょう!
ステップ2:譲渡所得を計算し、申告書を作成する
集めた書類をもとに、「譲渡所得の内訳書」で所得を計算し、「確定申告書」を作成します。建物の減価償却費の計算や、特例適用の判断が難しい場合は、無理せず税理士に依頼するのが確実です。
自分で作成する場合は、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」が非常に便利。画面の指示に従って入力すれば、税額計算から申告書の印刷(またはe-Taxデータ作成)までできます。市販の確定申告ソフト(例:マネーフォワード クラウド確定申告など)も使いやすいでしょう。
ステップ3:税務署へ提出する(期限厳守!)
作成した申告書と添付書類を、売却した年の翌年2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署へ提出します。
- e-Tax(電子申告):マイナンバーカードがあれば自宅からオンラインで完結。一番おすすめ。
- 郵送:税務署へ郵送。控えが必要なら返信用封筒同封。
- 税務署へ持参:窓口へ直接提出。期限間近は非常に混雑。
期限を1日でも過ぎると、延滞税などのペナルティや、特例が使えなくなるリスクがあります! 早めの提出を心がけましょう。
ステップ4:納税 または 還付
申告の結果、税金を納める必要がある場合は、原則として申告期限(3月15日)までに納付します。損失が出て税金が戻ってくる(還付される)場合は、申告から約1ヶ月〜1ヶ月半後に指定口座に振り込まれます。
不動産売却を成功させるために:専門家との連携がカギ

ここまで見てきたように、家の売却と税金は非常に複雑です。損せず、スムーズに進めるためには、プロの力をうまく借りることが賢明です。
信頼できる「不動産会社」は税金の相談もできる?
売却活動全体のパートナーとなる不動産会社。税金の計算や申告自体は税理士の独占業務ですが、信頼できる会社なら、
- 売却にかかる税金の概算を教えてくれる。
- 使える可能性のある特例について情報提供してくれる。
- 必要に応じて、提携している税理士を紹介してくれる。
- 確定申告に必要な書類(売買契約書など)をしっかり準備・説明してくれる。
といったサポートが期待できます。査定額だけでなく、こうした税金面での知識やサポート体制も、会社選びの判断材料にしましょう。
私たちリブネクストが、お客様の不動産売却においてどのようなサポートをさせていただいているか、「リブネクストが不動産売却で選ばれている理由」のページもぜひご覧ください。
税金のことは「税理士」に任せるのが一番安心!
譲渡所得の計算(特に取得費や減価償却)、どの特例を使うのがベストか、住宅ローン控除との兼ね合い…これらは非常に専門的で、判断を間違えると大きな損につながりかねません。
税金に関して少しでも不安や疑問があれば、迷わず「税理士」に相談しましょう。相談費用はかかりますが、それ以上の節税メリットが得られることも多いですし、何より「安心」が手に入ります。特に不動産売却に詳しい税理士を選べば、的確なアドバイスとスムーズな手続きが期待できます。
リブネクスト株式会社では、経験豊富な担当税理士とも連携しております。税金に関するご相談もワンストップで対応可能です。まずはお問い合わせフォーム・電話・LINEからお気軽にご連絡ください。
まとめ:家の売却と譲渡所得税、しっかり理解して賢く手続きを!
家の売却後の譲渡所得税と確定申告について、かなり詳しく見てきました。最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 家を売って利益(譲渡所得)が出たら、所得税・住民税(譲渡所得税)がかかる!
- 譲渡所得は「売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)」で計算。取得費の証明が超重要!
- 所有期間5年超(売却年の1月1日時点)で税率が約半分に!
- マイホーム売却なら「3,000万円控除」などの強力な節税特例を忘れずにチェック!
- 特例を使うなら(損失が出た場合も)必ず翌年に「確定申告」が必要! 期限厳守!
- 書類集めは早めに! 計算や手続きに不安があれば迷わず「税理士」に相談!
税金の話は難しく感じますが、ポイントを押さえれば大丈夫。正しい知識を武器に、賢く税金対策を行い、大切な資産である家の売却を成功させてくださいね。
尼崎で家・不動産の売却、そしてそれに伴う税金のご相談なら、リブネクスト株式会社へ!
「何から始めればいいかわからない」「税金のことが心配」…どんなことでも構いません。お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なプランをご提案します。
お問い合わせフォーム・お電話・LINEから、お気軽にご連絡ください!
→ リブネクストが不動産売却で選ばれている理由はこちら